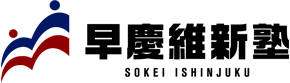算数「わからない」問題の対処法
皆さんこんにちは!早慶維新塾算数担当の野澤優子(のざわゆうこ)です。
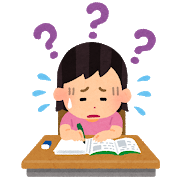
宿題をやっていて「わからない」問題が出たとき、お子さまはどうしていますか?
先生に質問しなさいと言ってます! という声が聞こえてきそうです。
そうです。その通りなのですが…
今回は「わからない」問題の「わからない」の部分に拘って
成績アップ→志望校合格へとつなげていくお話をいたします。
生徒から質問を受けたとき、
私は必ずどこがわからないか、何がわからないか、逆に質問します。
「わからない」問題は 大きく分けて4種類
① 問題を解く基礎知識がない(もしくは忘れている)から解けない、わからない。
③ 問題文や与えられたグラフや図の意味がわからないから解けない、わからない。
④ 見た目難しそうに見えるから無理だとあきらめるから解けない、わからない。
①の場合は忘れている知識を復習し定着させれば問題解決。
②の場合は、自信を持って解いた答えが間違っていると、「解答が間違ってます」
と言って、生徒が自分の解法を熱く語ってくれることもよくありますが、
解いていったプロセスを一緒に確認していくと必ずつまずきが見つかります。
そこを修正すればOK!
問題は、③と④のケースです。
通っている塾のシステムによって異なりますが、③④があまりに多いと、
宿題のレベルがその子にあっていないことになります。
ちなみに早慶維新塾のように一対一の完全個別で各教科担当制だと、それは考えにくいです。
③は問題を解く以前に問題文の整理ができないので、解く前に思考停止。
④はそもそも自分で考えることを拒否して、教えてくれるのを待つ他力本願の姿勢がNG。
お気付きだと思いますが、③、④に共通しているのは
問題を見た早い段階で考えることをやめてしまうことです。
「本気で成績を上げたい、志望校に合格したい!」と思うならば
どんな問題にあたっても、
「難しそう、無理だ…」ではなく
「難しそう、よし!解いてやる!」です。
まずは問題文を丁寧に読み、重要と思った語句や数字に線を引く。
なかでも速さの問題はちょっとした物語文のようなもの。(国語みたいと言われそう)
場面や条件が変わるのを図や表、グラフに描いてみることです。
そしてじっくり、整理しながら考える。
そうすると、新たに気付くことがあるかもしれません。
ここまで自分でチャレンジした後、先生に質問すると、
自分がどこでつまずいているか、何が足りなかったのかがよく分かるし、
問題が解けると「やればできるじゃん!自分」と自信につながります。
頑張って悩んで苦しんだ分、知識は定着・蓄積されていきます。
中途半端に取り組んで解説を聞くと、その場では理解でき、分かった気分になるでしょうが、
知識の定着・蓄積はあまりされません。定着させるにはまた別の努力が必要になるでしょう。
慣れないうちは時間がかかり、思ったように図や表は描けないかもしれません。
しかし続けていくと、だんだん的確に問題文を整理したり、図式化できるようになります。
そしてなによりも、
直ぐにあきらめないで丁寧に考えられるようになります。
そうなるとレベルアップ!
志望校合格へと一歩近づきます。
応援よろしくお願いします