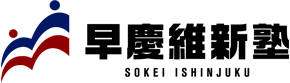受験の基礎教養とおとぎ話
皆さんこんにちは 早慶維新塾 国語担当 青山雄一(あおやまゆういち)です。
むかしむかしあるところに、おじいさんとおばあさんがいました。
おじいさんは山にしばかりに、おばあさんは川にせんたくにいきました・・・

この文章を読んで、何のことか全くわからない!ということはないと思います。
小さいころからいろいろなおとぎ話を読んできたと思います。
では、おとぎ話はなぜ読まれつづけるのでしょうか。
まずは、単純に話が(子どもにとって)おもしろいのでしょう。
これにはわかりやすいということも含まれます。
次に、物語で伝えたいことが分かりやすく、
普遍的であることが挙げられるのではないでしょうか。
「アリとキリギリス」というお話があります。
順風満帆なときでも油断せずに過ごさねばならない、
というように(多少の個人差はあれ)このお話にはこういう教訓があるとすぐにわかります。
ところで、国語の勉強として、おとぎ話を読んでもらいたいと思っています。
理由はいくつかあります。
一つ目に、読解の練習にちょうどいいからです。
勉強を意識しないで読むことが出来ます。
読み終わったらぜひ、内容をお子様に聞いてみてください。
どんなお話だったのか、どう思ったのか、教訓は何かなどいろいろなお話ができます。
逆にこちらからも感想を言ってあげることでこういう読み方もあると気がつくかもしれません。
次に、様々なものが出てくるからです。
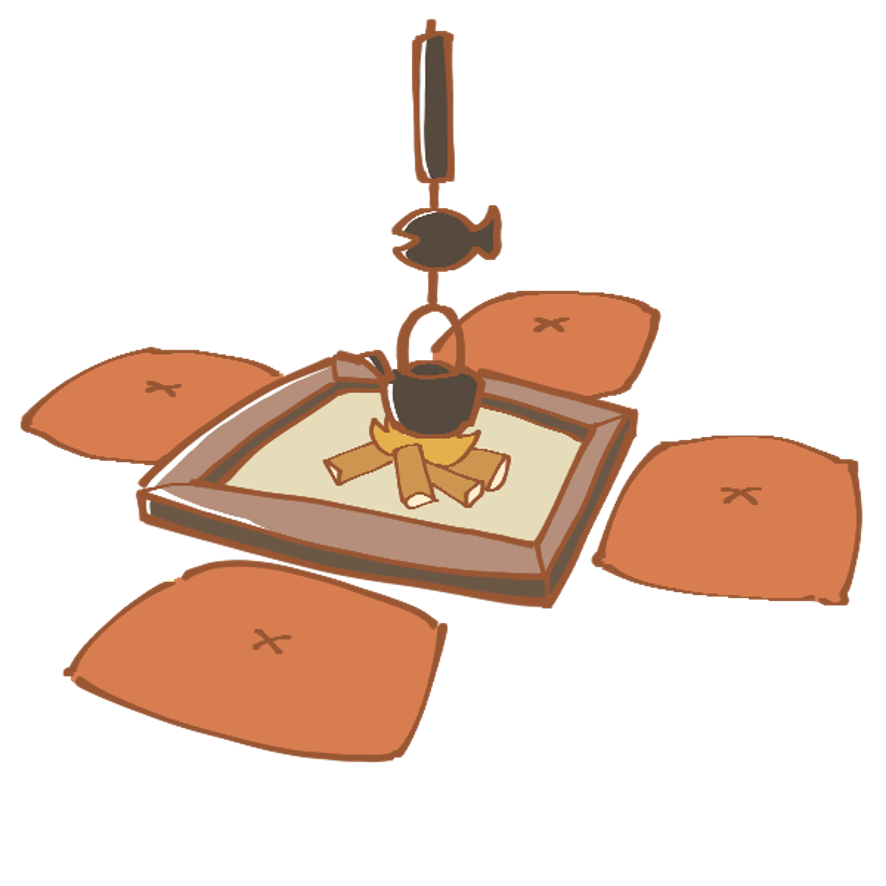
「いろり」「玉手箱」「笠」など子どもには意外と難しいものです。
大人でもむずかしいことがありますよね。
「おじいさんはやまにしばかりに」の「しば」って何か分からない人、意外と多いです。(ぜひ調べてみてください)
ここで身に付いた知識が、読解や他の科目でも役に立ちます。
絵本をつかい、ビジュアル的にも理解できると更にいいと思います。
最後に、おとぎ話の内容が普遍的なものだからです。
人間が生きていく上で大切なこと、人間の弱い所。
これらのことをおとぎ話から知っていることは、前提条件ではないでしょうか。
また、おとぎ話の内容そのものが一般教養である一面もあります。
いろいろな入試問題で昔話について触れられているのもその証拠でしょう。
小さいころから読んでくることが本来の姿です。
一方であまり読んでこなかったお子さんがいるのも事実です。
先日も浦島太郎を知らない生徒がいました。
もちろん知らないことは仕方ないことなので、それで怒ることはしません。
内容の確認をしますが、やはり、授業後に自分で読んでほしいなと思います。
もし今まで読んでこなかったならば今からでも読んでみてください。
様々な発見があると思います。(大人でも発見があると思います!)