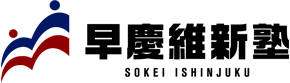年の瀬・年明けの過ごし方
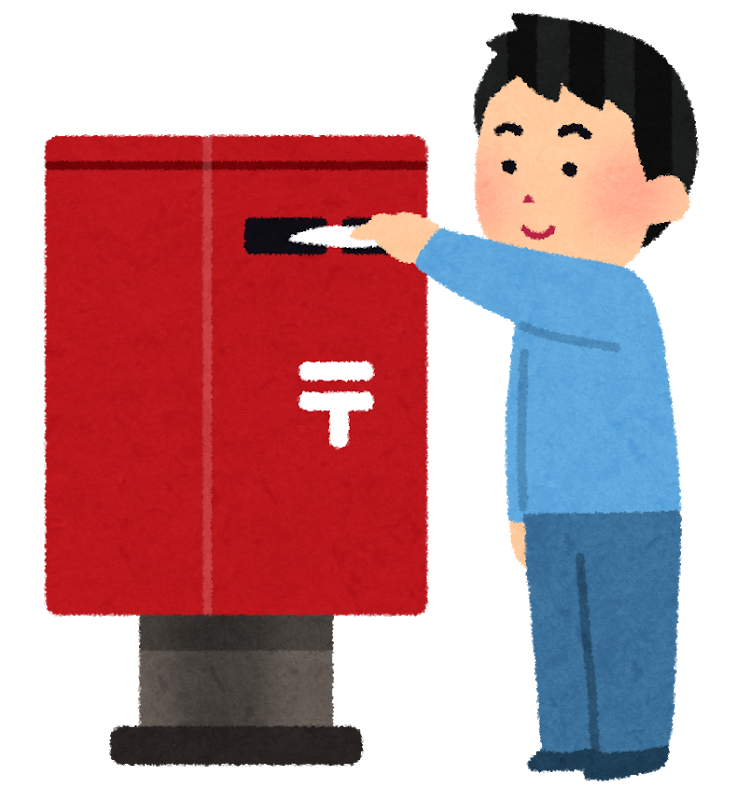
こんにちは。早慶維新塾・国語担当の青山雄一(あおやまゆういち)です。
いよいよ11月になりました。
朝晩の冷え込みが厳しくなってくるとともに,年末の気ぜわしさが出てきます。
この時期になると,年賀状をかかなくちゃ・・・と焦る時期でもあります。
さて,年賀状ですが,お子様はだしていますか?また,書くことはできますか?
手紙の書き方
こんなこと国語に関係ないと思うかもしれません。
いえいえ。そんなことはないのです!
中学・高校生の時に国語の授業で「便覧」というものを使っていませんでしたか?
この便覧。中を見てみると,手紙の書き方が出ています。
国語という科目は「日本語を読む・書く」ということが基本ですが,
その先には「日本語を使う」ということがあります。
文学作品を読むというのは,日本語を読み文章を味わうということです。
そして,日本語を使うなかには日常生活の中で日本語を使うということも入っています。
だから,手紙の書き方というのは国語という科目に入ってくるのです。
この場合の手紙というのは,授業中先生に見つからないようにしながら友達に回した手紙ではありません。
きちんとした書き方に基づいた手紙です。

では,入試問題を見て見ましょう
(日付と差出人を変えました。また,元は縦書きです。傍線など一部改変してあります。慶應中等部の過去問です)
〇〇先生
謹賀新年
旧年中は( A )
さて 今年の 干支は( B )ですね
そのイメージのようにのんびりという訳にはいかず
今は来月に迫った中学受験の追い込みで
昼夜勉強に励んでおります
「冬来たりなば春遠からじ」と言います
卒業までに残された時間もあとわずか
クラスの仲間と楽しい思い出を一つでも多く残したいです
そして 桜の咲くころには中学校へ進学します
新たな学校 また友人との出会いを待ち遠しく思います
それでは 本年もご指導よろしくお願い申し上げます
2020年1月1日 元旦 青山雄一
問1 謹賀新年とはどのような意味か,正しいものを選びなさい
1 新たな気持ちで新年のスタートを切ること。
2 つつしんで新年の喜びを申し上げること。
3 神様に願いや祈りを捧げつつ,良い年にしようということ。
4 初日の出のまばゆさにあふれて,新年を迎えること。
5 新年を迎え,冬の寒い時期に体を労わってほしいということ。
問2 ( A )に入れるのにふさわしい表現を考え,15字以上20字以内で書きなさい。
問3 「干支は( B )ですね」について
(1)「支」には動物が割り当てられるが,その種類は全部でいくつあるかふさわしいものを選びなさい
1 六 2 八 3 十 4 十二 5 十四
(2)( B )にあてはまる動物を選びなさい
1 いぬ 2 うさぎ 3 ひつじ 4 ねずみ 5 ねこ
問4 「冬来たりなば春遠からじ」の意味として最もふさわしいものを選びなさい。
1 冬が過ぎ去って,春が訪れた。
2 冬の長さに比べて,春の期間は短い。
3 冬がなかったら,春も来ない。
4 冬はきたけれど,春まではまだ遠い。
5 冬が来たら,春はそう遠くはない。
問5 次の1~5の指摘について,正しいものを一つ選びなさい。
1 「〇〇先生」の下に敬称である「様」が必要である。
2 「謹賀新年」の前に,冒頭文として「あけましておめでとうございます」という一行を入れるべきである。
3 「桜の咲くころ」ではなく「梅の咲くころ」と書くほうが時期としてふさわしい
4 「ご指導」より,「ご指導のほうを」と置き替えたほうが丁寧な表現となる
5 「1月1日」と書いているが,これは不要である。
いかがでしょうか?大人にはそんなに難しくはないと思います。
問1は2ですね。「謹んで(つつしんで)」という漢字が読めれば難しくありません。
問2は,何でもいいのでしょうが,年賀状の後半に「今年もご指導よろしくお願いします。」とあります。
それに対応させれば「勉強等ご指導いただきありがとうございます」あたりがよいでしょうか。
もちろん,ほかにも解答はたくさんありえます。
問3(1)は干支の数くらいわかるだろうと思いますが,意外と誤答が多いようです。
問3(2)これは,分かってほしいですね。来年はネズミ年です。
問4は大人なら簡単にわかります。5です。
問5はわかりましたか?正解は5です。「元旦」と「1月1日」は意味がかぶっています。
二重表現はやりがちな間違いですね。2の選択肢が間違いなのも,二重表現をしてはいけないからです。
勉強方法

さて,この過去問を見て,これを子供ができるようにするにはどうしたらいいか気になりましたか?
塾で教えてもらう,と答えた方は,半分は正解で,半分は不正解でしょう。
特に,問3や問5については,塾の授業でも対策はしやすいと思います。
しかし,問2などはどうでしょうか?
もちろん,私もできない生徒がいれば教えています。
しかし,いちから教えることはしていません。
なぜなら,教えなくてもできる生徒もたくさんいるからです。
聞いてみると,普段から年賀状を出している生徒は,かなりできるようです。
特に,学校の先生に出している生徒は何の抵抗もなく手が動きます。
(文字数が合わずに悩みだす生徒はいますが・・・)
中学受験をするときには,日常生活をきちんと送れているということはとても大切なことです。
日常生活とは,身の回りの整理整頓なども含みますが,年中行事なども日常生活の一つでしょう。
これから年末年始にかけていろいろな行事があると思います。
ご家庭でやってみてはいかがでしょうか?
冬至にはゆず湯に入り,カボチャを食べる。
年賀状を先生に書く。(出さなくてもいいので・・・)
年越しそばを食べ,紅白歌合戦を見る。
おせち料理を食べる。お雑煮を食べる。
初日の出を見る。
初夢が何だったか話題にする。
七草がゆを食べる。
その時に,ぜひ「今日は冬至だよ」「ゆず湯に入るんだよ」と確認してあげてください。
由来などはわからなければそれでいいです。
そういう習慣があるんだな,ということが確認できれば大丈夫です。
一度でも経験した生徒さんは,教えた時に「あれだ!」「やったことある!」という反応をします。
そこまでくれば覚えたも同然です。
そして,このようなことが中学受験合格への第一歩でもあるのです。
ただ机に向かってばかりいる年の瀬にしてはもったいないですよ!
色々なことを経験させてください。