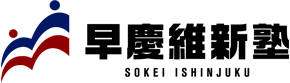スーパーへの買い物は学びの宝庫です!

早慶合格への道先案内人、
早慶維新塾 塾長 野田英夫です。
お子さんと一緒に買い物に行っていますか?
スーパーに連れていっていますか?
受験勉強で忙しいから・・・
そんなこと言っていると大切な学びの機会を失ってしまいますよ。
さらに、受験にも影響してしまいますよ。
詳しくはこのあと書きますね。
著書「御三家はわかりませんが早慶なら必ず合格させます」がまだまだ好評発売中です。
まだ読んでいない方は、書店にお急ぎください。
もうすぐ重版出来!
- 塾長が明かす大手塾では決して教えない
早慶合格への最短ルート
◆早慶に合格できる3つの理由
◆「普通の子」が早慶に合格できるための勉強法
◆面接で試験管は何をみるのか早慶中学完全合格マニュアル発売!
基礎学力の前に「感覚的学力」が必要です!
聞きなれない言葉が出てきました。
「感覚的学力」
これですが、
基礎学力の根底に位置するものです。
応用学力
基礎学力
感覚的学力
このような感覚です。
すべての学力の根底にあるものです。
「感覚的学力」が土台となり、
基礎学力が上に乗り、
さらに応用学力が上に重なるイメージですね。
だから「感覚的学力」を身につけないで、
基礎学力、応用学力を重ねようとしても、
上に積みあがらず、しっかりした学力は身につかないのです。
「感覚的学力」ってなに?
では、「感覚的学力」とはどんなものなのか?
日常生活から身につけられる感覚的なもの。
なかには社会的常識もあります。
例えば、「重さ」
鉄は重い、ステンレスだったら軽い。
しかし、持たせてみないとわからない。
さらに、紙は軽いが、
コピー用紙一束だったら結構な重さになる。
ペットボトルだって、
350㎖だったら軽いけど、
2ℓのペットボトルだったらかなり重い。
また、「距離感」
1キロってどれくらいの距離なんでしょうか?
車に乗って移動していたら1キロの距離感はわかりません。
一度でも、1キロを歩いてみないとわかりません。
歩いてみたら18分くらいかかりました。
1キロって結構な距離なんですね。
そのような感想も出てくるかもしれません。
感覚的学習というのは、
経験させないと身につかないものなんです。
お子さんはこの感覚的学力が身についていますか?
「あたりまえじゃない」と思わないでください。
最近の子どもは結構、わかりませんよ。
特に、低学年から進学塾に通わせている中学受験生は、
この感覚的学力が身についていません。
感覚的学習というのは、
経験していないと身につかないものです。
ですから、
なんでも親がやってあげていたら、
感覚的学力は身につかないんです。
効率を考えて、
親がやってあげていると感覚的学力は身につかないんですね。
では、質問します。
鉄アレイ2キロは水に浮かびますか?

もちろん浮かばず沈みますよね。
では、2ℓの水のペットボトルだったらどうでしょうか?

また、2ℓの濃縮果汁のオレンジジュースだったらどうでしょうか?

さらに、20キロの小学生は水に浮きますか?

解答はこのあと書きます。
このようなことを、
塾の授業で学ぶと「知識」として身についたことになります。
しかし、経験を伴って学習しないと、
「知恵」にはならないんです。
積極的にお手伝いをさせましょう!
このように経験をさせないと、
「感覚的学力」は身につきません。

だから、お子さんにはお手伝いをさせてください。
特に、お勧めしたいのは、
一緒に買い物に行くことです。
子どもを連れてスーパーへ買い物に行きましょう!
そして、お手伝いさせるのです。
買い物かごを持たせてください。
そして重くなってきたら、
カートを使っても構いません。
ミネラルウォーターを1ケース買う場合も、
最初に買うと重いので、
最後に買った方が効率的ですね。
ちなみにウチの娘(小学1年生)は、
アイスの「ガリガリ君」が好きで、
以前は真っ先にアイスコーナーへ向かおうとしていました。
しかし、最初に買ってしまうと、
溶けてしまうので、最後に買うように学習しました。
ちなみに、冷凍コーナーは、
入口からは遠い、レジに近い場所にあるのはこういう意味があるのだと思います。
果物の「桃」を買いたい場合、
桃はものに触れると傷みやすいので、
カゴの下には入れず、上に物は載せない。
でも、成果売場は店の入口付近にありますので、
入れ方に工夫が必要です。

会計の際のレジの並び方にもコツがありますよね。
カゴにたくさん入っているお客の列に並ぶと時間がかかりますよね。
レジを打つ店員にも注目していませんか?
ベテラン店員の列だと早く進みますよね。
レジの流れを読むのも勉強になります。
このように感覚的学力を養うのに、
スーパーでの買い物は絶好の場所といえます。
受験勉強を優先させて、
効率ばかりを考えてしまうと、
感覚的学力は身につきませんよ。
入試でも問われる感覚的学力
最近の入試では、
答えが一つにならない、考えさせる問題が増えています。
また、テキストに載っていない出題も増えています。
慶應附属校では、以前からこのような出題がありました。
最近では、慶應に限らず大学附属校の多くで見られるようになりました。
さらに、公立の中高一貫校の適正検査でも出題されています。
以前の入試問題のような知識量を問う入試ではなくなっています。
つまり暗記量を問う問題ではないのです。
少しでも早く勉強した方が有利と考え、
低学年のうちから進学塾に入塾させ、
知識を詰め込み、
そして効率を優先し、
なんでも親がやってしまっていると、
経験を伴う感覚的学力は身につかず、
ホンモノの学力にはなりませんよ。
これは生き抜く力にもなるのです。
最後に、
先ほどの解答です。
① 2ℓの水のペットボトルは水に浮きますか?
答え 浮きます。
② 2ℓの濃縮果汁のオレンジジュースだったらどうでしょうか?
答え 沈みます。
③ 20キロの小学生は水に浮きますか?
答え 浮きます。しかし、下手に動くと沈みます。
なぜこのような結果になるのかは、子どもと一緒に考えて、調べてみてください。
私はこれからも思っていることを本音で書いていきます。
塾業界で蔓延している非常識を明らかにしていきます。
皆さんに少しでも早く目を覚ましてもらうために!
正しい情報を積極的に収集してください。
情報というのは、弱者のためにあるのではありません。
強者のためにあるのです。
情報強者となってください。
知らなかったでは済まされないのですから。
では、また!
もし、受験のことでお困りのことがありましたら、
野田英夫がカウンセリング(無料)を実施します。
お気軽にご連絡ください。
また、コメント、メッセージも頂けると執筆の励みになります。
contact@altair-waseda-keio.jp