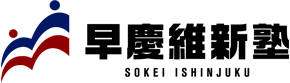慶應・早稲田中学受験 小学生 読解力をつけるには
こんにちは。早慶維新塾 国語担当の青山雄一(あおやまゆういち)です。
2月になり一通り今年度の中学入試も終わりました。
5年生のお子さまは来年に向けて受験勉強を本格化させていく時期でもあります。
さて、国語の文章問題が苦手というお子さまが多くいます。
授業を担当していると、そのようなお子さまの多くが
文章を読んでいないという場合が少なくありません。
そのような時にどうしたらいいのかということを考えてみます。
実際に担当していた生徒さんで次のようなことがありました。
「彼が走っていると、ドンという太鼓の音が聞こえた。」という文章があり、
それに対する問いがありました。
問いは「彼は何の音を聞きましたか?」というものです。
それに対する生徒さんの解答は「ドンという音」というものでした。
「どのような音を聞きましたか」なら「ドンという音」が正解になります。
しかし、この場合は「何の音を聞きましたか?」という問いですから
「太鼓の音」が正解になります。
私が何も言わずに×印をつけると、
生徒さんは慌てて「間違えた」といいながら答えを書き直します。
そこには「走っていると聞こえた」という回答がありました。
もちろんこれも不正解です。
生徒さんの頭の中は
間違えちゃった、違うことを書かなくちゃ、
ということでいっぱいです。
もう、何を問われているのか
冷静に考えることは出来なくなっています。
そこで、私は生徒さんに
問いを音読するように指示をしました。
生徒さんは問いの音読を始めます。
しかし、とても速く音読をしているのでもっとゆっくりと音読するように伝えます。
すると、「問い/彼は/何の/音を/聞きましたか?」というように読んでくれます。
そこですかさず「答えは何?」と聞くと「太鼓の音」と答えられます。
多くの生徒さんは、黙読すると単語を読み飛ばしてしまいます。
頭の中は答えを書かなくちゃ!ということでいっぱいです。
そして「こんなことを聞かれているんだろう」
と決めつけて答えを書いてしまいます。
ですから、ゆっくりと丁寧に音読するのです。
たった一行の問いですら黙読できないのですから、
本文になるともっと大変です。
本文を音読させると様々なことが分かります。
読めない漢字が出てきたり、変なところで切ったり。
意味の分からない言葉があるということですが、
飛ばしてしまっています。
そして、意味の確認もせずに終わらせてしまう。
これでは、問いに答えられるはずありませんし、
国語の成績も上がりません。
四谷大塚のテキストで
「音読してから答えましょう」
と書いてある問題がありますが、
音読というのは内容を確認するためにはとても効果があります。
大人でも新聞を読んでいて
ちょっと難しい文章に遭遇した時に、音読すると分かることがあります。
音読すれば必ずすべての単語を見て、声に出しますから理解が深まります。
塾の自習室で音読するというのは難しいかもしれませんので、
家で問題演習をするときに音読するということを試してみてください。
もし可能ならば、お子さまが音読しているときに
つっかえるところがあったら
言葉の意味を確認してみてください。
さらに、音読が終わったら、
どんな内容の文章だったのかを聞いてみてください。
繰り返しやっていくと
文章の内容をたくさん言えるようになっていきます。
ここまで出来るようになったら、
黙読する時に「声は出さないが音読するつもりで」という指示を出します。
音読が出来るようになっているわけですから、
黙読も以前に比べて出来るようになります。
学校の宿題で音読の宿題などがでることが多いようです。
音読は効果があるので宿題で出ています。
せっかくですからそのような宿題も真剣に取り組んでみてください。
このような努力が読解力につながります。