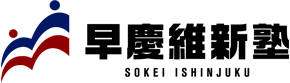進学校と附属校の入試問題が違うというのは本当ですか?
保護者がお持ちの悩みを
中学受験カウンセラー野田英夫が解決するブログです。
保護者からいただいた相談メールにズバリ回答いたします。
【相談内容】
進学校と附属校の入試問題が違うというのは本当ですか?
(小5のお母さんから)
先生のご著書を読んだお母さんから、
「進学校と附属校の出題が違う」と聞きました。
また、志望校についても、
「進学校と附属校の両方を志望しない方がいい」とも聞きました。
その辺を詳しく教えていただけないでしょうか。
いまの志望校は、慶應中等部と難関進学校のひとつを考えています。
野田先生、よろしくお願いします。
【回答内容】
早慶合格への道先案内人、
早慶維新塾 塾長 野田英夫です。
著書「御三家はわかりませんが早慶なら必ず合格させます」が好評発売中です。
すごい勢いで売れています。
まだ読んでいない方は、書店にお急ぎください。
実は、そのとおりです。
進学校と附属校の入試問題は大きく異なります。
では、なぜ進学校と附属校の問題は違うのでしょうか?
進学校と附属校では入学後の勉強がまったく違う
それは学校入学後の勉強が異なるからです。
進学校といわれる学校ではどんな勉強がされていますか。
進学校というのは、
6年後の大学受験に対応できる学力を身につける学校ですよね。
大学への進学を目的とした学校ということです。
だから、「進学校」と呼ばれます。
進学校を志望する保護者は、
6年後に、国立、早慶などの一流大学に進学できることを期待して入学させます。
だから、その学校の大学進学実績が人気を左右しますよね。
進学実績が高い学校は人気となり、
そうでもない学校は人気があまりない。
学校側としては、その6年間に対応できる生徒を求めることとなります。
その6年間に耐えうるかどうかを入試問題で判断することとなります。
6年間指導して、難関大学へ合格できる可能性のある生徒に入学して欲しいということです。
一方、附属校はどうでしょうか。
最近は、さまざまな形態の附属校があります。
「半進学校」といえるような他大学受験を推奨している学校もあります。
しかし、早稲田・慶應の附属校(系属校)については、
そのほとんどが早稲田大学と慶應大学に進学することを目的としています。
附属校というのは、基本的な考え方として、「大学受験がない」といえます。
附属校に行ったら楽ができるのか?
では、附属校に進学したら、
6年間まともに勉強しなくていいのでしょうか。
その答えはNoといえます。
しっかり勉強しないといけません。
ただし、勉強といっても大学に入るための受験勉強ではありません。
どの附属校でも、力を入れているのが「実学」と呼ばれている勉強ですね。
つまり、実生活の役立つ学問のこと。
社会に出てから通用する、使える学問を身につけるための授業が多く行われています。
よく「楽がしたいから附属校に行きます」ということを耳にします。
これって間違っています。
楽はできません。附属校は、楽チンではありません。
課題が多く、レポート提出なんて日常茶飯事です。
学校側としては、
自ら学ぼうとする積極思考できる生徒を求めています。
これは勉強だけではありません。スポーツでも同じことがいえます。
例えば、サッカーを思い切りしたいから附属校へ行きたいは、
積極思考ですからいいわけです。
このように、進学校では大学受験に対応できる生徒を求めています。
また、附属校では積極的に学ぼうとする生徒を求めています。
進学校と附属校では出題傾向が異なる!
求める生徒が違うわけですから、
当然ながら、入試問題も異なるのです。
一概にはいえませんが、
進学校の方が難易度は難しくなる傾向があります。
さらに、進学校の出題は、論理的思考を問うものが多いといえます。
早慶は、普通の子でも合格できる!
附属校の代表である早慶中学は、
「普通の子」でも十分に合格できると言い続けています。
早慶中学の出題は、普通の子でも十分に解答できる問題だからです。
言い換えると、しっかり努力を重ねていけば、普通の子が合格できる学校です。
簡単だと言っているのではありません。
効果的な努力と学習を積み重ねれば、普通の子であれば合格できるという意味です。
御三家は、早熟な子でないと合格できない!
しかし、進学校でも難関進学校だと、こうは言えません。
特に、御三家やそれに次ぐ学校は、普通の子が皆、合格を勝ち取れるとはいえません。
よく言われることですが、
御三家などの難関進学校は、
「早熟な子」でないとなかなか合格できません。
進学校と附属校の両方を志望しない方がいいのか
さて、もう一つの質問にも回答いたします。
「進学校と附属校の両方を志望しない方がいいのか」ですが、
基本的には、どちらかにした方がよいと考えます。
先ほど回答したとおり、
進学校と附属校の入試問題は異なります。
そのため、進学校用の受験勉強と附属校用の受験勉強の両方をしないといけないからです。
2倍の勉強になるわけではありませんが、
付加は増えることになります。
それだけ進学校と附属校の出題傾向は異なります。
ちなみに、進学校と附属校を大きくふたつに分けて説明してきましたが、
附属校のなかでも各学校で出題傾向は大きく異なります。
例えば、同じ慶應附属だとしても、
慶應義塾「普通部」の問題と、
慶應義塾「中等部」の問題は、全然違います。
だから、まったく方法性の異なる、
進学校と附属校を両方受験するとなると、
更なる「付加がかかる」ということになるのです。
効率的ではないともいえます。
では、また!
皆さまからの質問持っています。