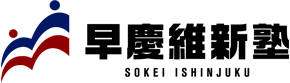十干十二支は、社会科の中でも多く使われているのです!!
皆さんこんにちは。早慶維新塾社会担当の望月裕一(もちづきゆういち)です。
今回のテーマは、
「十干十二支(じっかんじゅうにし)は、社会科の中でも多く使われているのです‼」です。
前回のブログでは、「干支」についてお話しました。
(ちなみに、どんな内容だったかは、9月7日のブログをご確認ください。)
言葉自体は、あまり聞きなれていない方も多いですよね?
「十干(じっかん)」とは、古代中国で考えられた思想から作られたもので、
陰陽(いんよう)・五行(ごぎょう)説などと深く結びついています。
では、「十干」とは何かを見てみましょう!!
「十干」とは、
甲(こう)・乙(おつ)・丙(へい)・丁(てい)・戊(ぼ)
己(き)・庚(こう)・辛(しん)・壬(じん)・癸(き)
のことです。
この「十干」と前回のブログでお話した「十二支」と合わせて、
「十干十二支(じっかんじゅうにし)」と言います。
「十干十二支」は、中学入試の社会科と密接な関係にある
ということを知っていましたか?
事実、中学入試の地理と歴史で数多く出てきますので、
しっかりと覚えておきましょう!!
ちなみに、どんなところで出てくるのかと言うと・・・。
① 地理
子午線(しごせん)
「干支」は方位を表すのに用いられます。
その中で、子(ね・し)は「北」を、「午」(うま・ご)は「南」をそれぞれ表します。
よって、子午線は地球上の南北を結ぶ線=緯線を表しています。
② 歴史
「干支」は、暦を表すのに用いられ、60年に一度同じ干支がめぐってきます。
「干支」はご存知の通り、12種類あります。
そして、「十干」は10通りですので、西暦の下一桁と次のように対応します。

壬申の乱 【672年=壬申(じんしん)】
壬申の乱は、天智天皇(中大兄皇子)の死後、次の天皇の位をめぐる争いです。
天智天皇の弟大海人皇子と天智天皇の子大友皇子が対立し、
大海人皇子が勝利しました。
後に大海人皇子は、即位して天武天皇となりました。。
戊辰戦争 【1868年=戊辰(ぼしん)】
戊辰戦争は、旧幕府軍と明治新政府軍の戦いです。
鳥羽・伏見の戦い(1868年1月27日~1月31日)から
五稜郭の戦い(1868年10月~1869年5月17日)までの戦いを総称して、
戊辰戦争と言います。
五稜郭の戦いでは、新撰(選)組の元副長であった土方歳三の活躍が有名ですね。
甲午農民戦争 【1894年=甲午(こうご)】
甲午農民戦争は、朝鮮で起きた農民の反乱です。
この戦争の処理をめぐって、日本と清の対立が激化し、
日清戦争へと発展していきました。
辛亥革命 【1911年=辛亥(しんがい)】
辛亥革命は、1911年から1912年にかけて、清で発生した共和革命です。
名称は、革命が勃発した1911年の干支である「辛亥」にちなんでつけられました。
辛亥革命では、孫文らが中心となって、清王朝を倒し、中華民国を誕生させました。
ちなみに・・・。
甲子園(こうしえん)
春・夏の高校野球で有名な甲子園は、球場が完成した年が
1924年の干支である「甲子」だったため、「甲子園球場」と名付けられました。
皆さん、どうでしたか?
このように「十干十二支」は社会と密接に関係していることがわかりますよね。
是非、今回のブログを参考にして、お子さまと「十干干支」について話してみてください。
次回のブログもお楽しみに!!